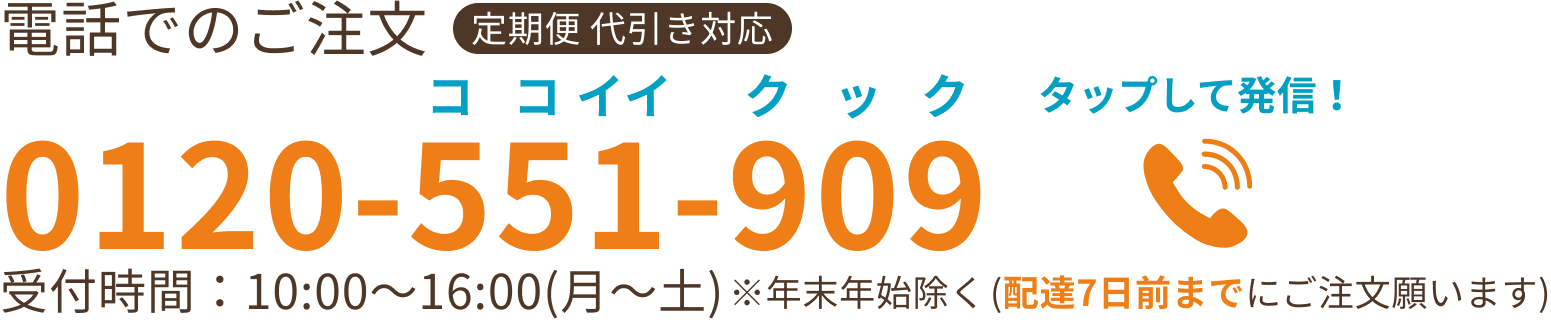透析治療を始めると、「リンの値が高いですね」、「リン制限の食事にしてください」と言われることがあるかもしれません。
しかし、「リン」という言葉にピンとこない方も多いのではないでしょうか。
リンってどんな成分?摂り過ぎるとどうなるの?
そんな疑問を解消し、食事でリンをコントロールするためのポイントをご紹介します。
1.リンとは?体内での役割と基礎知識
リンは、生き物のエネルギー代謝に必須の成分です。
また、カルシウムとともに骨や歯の素となったり、細胞膜や遺伝子などの構成要素として使われたりと、からだをつくるために欠かせない栄養素でもあります。
ヒトのからだの中では作ることができないミネラルで、食事から摂り入れる必要があります。植物や動物、さまざまな食品に幅広く含まれているため、通常は欠乏することはめったにありません。むしろ、加工食品に添加物として用いられるリンも多く、過剰摂取にならないよう注意が必要です。
食事から摂ったリンは、腸から吸収され、血流にのって全身に運ばれ、カルシウムなどといっしょに骨に蓄えられます。余分なリンは腎臓の働きによって尿中に排泄され、血中リン濃度は一定に保たれています。
2.腎臓とリンの関係 摂り過ぎのリスクと検査基準値
腎臓の働きが低下すると、リンの排泄ができなくなり、体内に溜まって、高リン血症になってしまいます。ビタミンDをつくる機能も弱まるため、カルシウムの吸収がしづらくなり、低カルシウム血症にもなりやすくなります。すると、リンとカルシウムのバランスを調整する副甲状腺ホルモンが活発になり、カルシウムやリンを過剰に骨から溶かし出そうとしてしまうのです。
カルシウムやリンを溶かし出した骨はもろくなり、骨粗しょう症につながります。さらに、高リン血症が続くと、過剰なリンとカルシウムが血中で結合し、関節や血管内に沈着することで、関節の痛みや運動障害、動脈硬化、ひいては心筋梗塞などの原因になります。
透析導入後の血中リン濃度の検査基準値は、3.5~6.0 mg/dLです。この検査値を保つことを目標に、食事からの摂取量をコントロールし、高リン血症を防ぎましょう。
3.透析とリン-摂取量の目安とポイント
透析の食事療法基準では、高リン血症予防のため、食事からのリン摂取量の目安が示されています。
1日当たりのリン摂取量:たんぱく質摂取量(g) × 15mg 以下
※ たんぱく質摂取量の基準:標準体重1kgあたり 0.9~1.2g/日
※ 標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
例えば、身長165cmの人なら、標準体重は60kg、たんぱく質摂取量は54g~72g/日が目安です。たんぱく質摂取量を60g/日とすると、リンの摂取量の目安は900mg以下/日となります。
リンは、たんぱく質が豊富な食品に多く含まれます。透析導入後は、たんぱく質は必要量を確保しつつ、リンは控える必要があるため、比較的リンの少ないたんぱく質食品を選ぶようにすると良いでしょう。
また、同じ量のリンを摂取しても、リンの種類によって吸収率がちがうこともあります。生き物に含まれるリンは有機リンといい、動物性食品では40~60%、植物性食品では20~40%の吸収率であるのに対し、加工食品の添加物に使われる無機リンは、90~100%の吸収率といわれています。加工食品は量や頻度を減らし、リンの吸収率が低い植物性の食品を積極的に摂り入れることもおすすめです。
4.リンを多く含む食品・リンが少ない食品
たんぱく質食品のうち、比較的リンが多い食品・少ない食品を知っておくと便利です。「リン/たんぱく質比(mg/g)」で表され、この値が低い食品を選ぶようにすると良いでしょう。
また、以下のポイントも覚えておくと安心です。
- 骨にはカルシウムとともにリンも多く含まれるため、うなぎ、しらす、小魚などの骨ごと食べられる魚は注意しましょう
- たらこ や いくら などの魚卵も、リンが多い食品です
- ハム、ソーセージなどの加工肉、ちくわなどの練り製品は、リン酸塩等の添加物が使われていることが多いです
- 「結着剤」、「乳化剤」、「pH調整剤」等の添加物は、無機リンを使用している可能性が高いため、原材料表示を確認し、使用する量や頻度を控えるようにしましょう

5.リンにも配慮された、安心のメディクック宅配弁当
リンの量が1食当たり300mgに計算された、『メディクック宅配弁当』。
製造時には余計な添加物を入れず、加工食品は成分値や原材料が明らかなものだけを使用。エネルギー・たんぱく質・塩分・水分・カリウム、透析で気になる成分も、食事療法基準に沿った栄養価に合わせています。
自宅に届いたら、冷凍庫にストック。食べたいときに電子レンジで温めるだけ。
リンの摂り過ぎが気になる方も安心の冷凍弁当を、透析生活に取り入れてみませんか?
まとめ
リンは生き物にとって重要な栄養素ですが、腎臓病や透析治療中の方は摂取量を制限する必要があります。
丈夫な骨と健康な血管を守って元気に透析生活を送るために、高リン血症を防ぐ食事のポイントを知り、無理のない範囲で実践していきましょう。
参考文献
- 日本透析医学会雑誌 45巻4号
- 日本透析医学会『慢性透析患者の食事療法基準(2014)』
- 文部科学省 食品成分データベース
あわせて読む: 透析とカリウム-野菜や果物は食べちゃダメ?